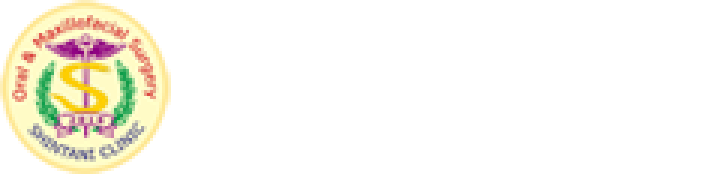無呼吸症候群・いびきの快眠歯科 Osas

10
いびき・睡眠時無呼吸症候群
症状の改善に快眠歯科

健康で充実した毎日を過ごすために、睡眠は非常に重要な役割を担っています。
パートナーがいる場合は、個人だけの問題だけではなく、一緒にいるパートナーの健康を害することにもなってしまう可能性もあります。
当院の快眠歯科は、快適な睡眠の妨げになる「いびき」「睡眠時無呼吸症候群」に対して、適切な治療を行い症状の改善を図ってまいります。
いびき・OSASとはSnoring and OSAS
あなたは いびき をかいていませんか?
大きな「いびき」や特に呼吸が止まる「いびき」は要注意なのです!!
その いびき は睡眠時無呼吸症候群かもしれません。
最近話題となっている『睡眠時無呼吸症候群』は、夜間睡眠中に10秒以上呼吸が一時停止すること(無呼吸)が7時間中30回以上、または1時間中5回以上起こる病気です。
いびき

いびきが発生する場はのど(上気道)です。肥満や飲酒、老化その他の原因で舌根が落ち込んで狭くなったのどに無理やり空気を通そうとするといびきが生じます。いびきをかく事自体は病気ではありませんが、呼吸がしずらくなっている状態といえます。
睡眠時無呼吸

睡眠時無呼吸は、のど=上気道=空気の通り道が完全に詰まってしまうことで生じます。いびきといびきの間にまるで呼吸がとまってしまうようないびきをかく人は『睡眠時無呼吸症候群』の可能性があります。
治療をせずに放置しておくと、高血圧リスク2倍、動脈硬化、不整脈、狭心症、心筋梗塞などリスク3倍3倍、脳梗塞などリスク4倍、交通事故リスク7倍、ED(勃起障害)など生命に危険が及ぶ場合もあります。適正な症状分析と診断、治療、予防などの対策が必要になります。
眠っている間に呼吸が数十回、ときには数百回と止まるようであれば、体内の酸素不足が深刻になってくるでしょう。また、無呼吸によって夜間に充分な睡眠がとれないため、昼間に強い眠気が起こり日常生活に支障をきたすだけでなく、放置しておくと合併症が併発する場合もあり早期に適切な治療を行うことが大切です。
- 朝の目覚めが悪い。何時間寝てもどうも頭がすっきりしない。熟睡感が無い。
- 朝起きたときに頭痛がする。
- 日中に眠気がある。会議中、パソコン、運転、テレビを見ているときなど。
- 夜中にトイレに起きる回数が多い。
- 何となく夜の生活から遠ざかっている。
- 肥満があり、よくいびきをかく。
- 睡眠中、呼吸がとまり、呼吸が再開するときに大きないびきをかく。
- 夜中によく目が覚めてしまう。
- 大きないびきをかいている。
いびき・OSASの原因Causes of Snoring and OSAS
いびき・OSASの原因は下記の12項目があげられます。
肥満
肥満になると、のど=上気道の内側にも脂肪がつき、上気道が狭くなり、呼吸時の空気抵抗が大きくなるために、いびきをかきやすくなります。
口呼吸
イビキをかく人のほとんどが口呼吸をしています。
仰向け(上向)で寝る
仰向けで寝ると舌がのどに落ち込みやすくなり、上気道が狭くなり、いびきをかきやすくなってしまいます。
鼻の疾患
鼻に疾患があると、鼻で息をすることが難しくなりますので、口呼吸となりをしてしまい、いびきをかいてしまうようになります。
あごが小さい(噛み合わせが悪い)
あごが小さく、噛み合わせが悪い人は、いびきをかきやすかったり、睡眠時無呼吸症候群(OSAS)になりやすい傾向にあります。
舌の肥大
舌が大きい人は、呼吸した時の空気抵抗が大きくなり、いびきをかきやすくなります。
咽頭扁桃、口蓋垂(のどちんこ)の肥大
疲労(ストレス)肉体的疲労
アルコール(飲酒)
薬(睡眠薬・精神安定剤)
老化(加齢)
室内(寝室)の気温や湿度
口呼吸と鼻呼吸mouth breathing and nasal breathing
鼻腔(びこう)には、「外部から入り込む異物や細菌を防ぎ排出する」「吸う空気を温める」「乾燥した息に湿り気を与える」といった働きがあります。しかし、口呼吸では、吸った空気が直接肺に入るため、風邪をひきやすくなる、空気中に含まれるホコリやダニなどのアレルゲン物質を取り除くことができずアレルギー症状が出やすくなるなど、さまざまな病気や症状の原因になります。
口呼吸が原因で起こる病気・症状
- いびき
- のどの疾患
- むし歯
- 頭痛
- 慢性疲労
- 鼻汁過多
- 味覚障害
- ドライマウス
- 口内炎
- 風邪を引きやすい
- 歯ぎしり
- アレルギー症状が出やすい
いびきと口呼吸
いびきは、口を開けて寝る(口呼吸)時に軟口蓋や舌根(舌の奥の方)が咽頭(のど)の方に落ち込み、上気道が狭くなり、出入りする空気が狭くなった上気道を振動させることが大きな原因です。様々な病気や肥満、その他一時的な疲れやアルコールの影響も関係します。
いびきの状態がひどくなり、軟口蓋などが気道を完全に塞ぐために呼吸が途切れる状態が、睡眠時無呼吸症候群で、睡眠レベルが浅くなり、熟睡ができないため、昼間眠たくなるばかりではなく、血圧や健康状態に非常に悪い影響を及ぼすことになります。
通常、鼻呼吸を行っている人は睡眠時に、舌先が前歯部に吸いつき、気道が広く保たれています。気道を確保するためには、口唇を閉ざす必要があります。いびきをかく人は口呼吸習慣があるため、睡眠時に前歯部に吸い付いていた舌が離れて、舌根がのどに落ち込む結果、いびきやさらに進んで睡眠時無呼吸症候群を合併します。
歯ぎしり
上下の歯が噛み合った状態で大きな力(通常時の8倍と言われています)で顎をずらす時に、歯と歯がきしんで音が出る状態をいいます。
歯ぎしりと口呼吸
「口を開けて寝ている人に歯ぎしりはないんじゃないの?」と思われている方へ
熟睡・安眠
リラックスして眠っている時は、上下顎の歯と歯の間が1㎜ほど開いた状態で、口唇を閉ざして鼻呼吸をしているのが理想です。これに対して口呼吸をしていると急に歯を食い縛たり、歯ぎしりを始めることがわかっています。
これは、咀嚼筋・表情筋・舌筋群など、顔と口・顎を構成する筋肉群が元来すべて内臓の筋肉と同じ由来であり、起きている時の交感神経の過緊張(ストレス)をそのまま睡眠に持ち込んで、これらの筋肉が痙縮して、くい縛り運動、歯ぎしりを反復性に繰り返すことになります。
硬い枕で横向き寝をすると必ず下顎の歯の一部が、上顎の一部の歯に斜めに当たるため、なお、不均衡な片側のみのくい縛りが発生し、歯ぎしりにつながります。
横向き寝の口呼吸では必ず顎が咀嚼(ものを食べる)時に近い運動をし、歯ぎしりの原因になります。
歯ぎしりを防ぐには、腹式呼吸ではなく横隔膜で十分に呼吸ができるように鼻呼吸を行い、副交感神経優位になるようにゆったりと、上向き寝で、やわらかい枕で頭の位置が1㎝位ゆったりと頭を沈めます。そのようにすると、上下顎の安静位(歯と歯の間が1㎜位開く状態)が保たれ、鼻腔から気管に至る気道がほぼ一直線に保たれ、最も安定した呼吸の下に安眠することができます。
通常、鼻呼吸を行っている人は睡眠時に、舌先が前歯部に吸いつき、気道が広く保たれています。気道を確保するためには、口唇を閉ざす必要があります。歯ぎしりをする人は口呼吸習慣があるため、睡眠時に前歯部に吸い付いていた舌が離れて、舌根がのどに落ち込む結果、いびきやさらに進んで睡眠時無呼吸症候群を合併します。
いびき・OSAS 診断検査の流れ
-
STEP 1
- 問診
- いびきに関する問診をします。
-
STEP 2
- 審査
-
治療用マウスピース作成のための歯や粘膜の状態を審査
- 口腔内模型作成
- レントゲン検査
- CT検査
- 呼吸検査
-
STEP 3
- 治療開始
- 治療用マウスピースによるいびき・OSASの治療